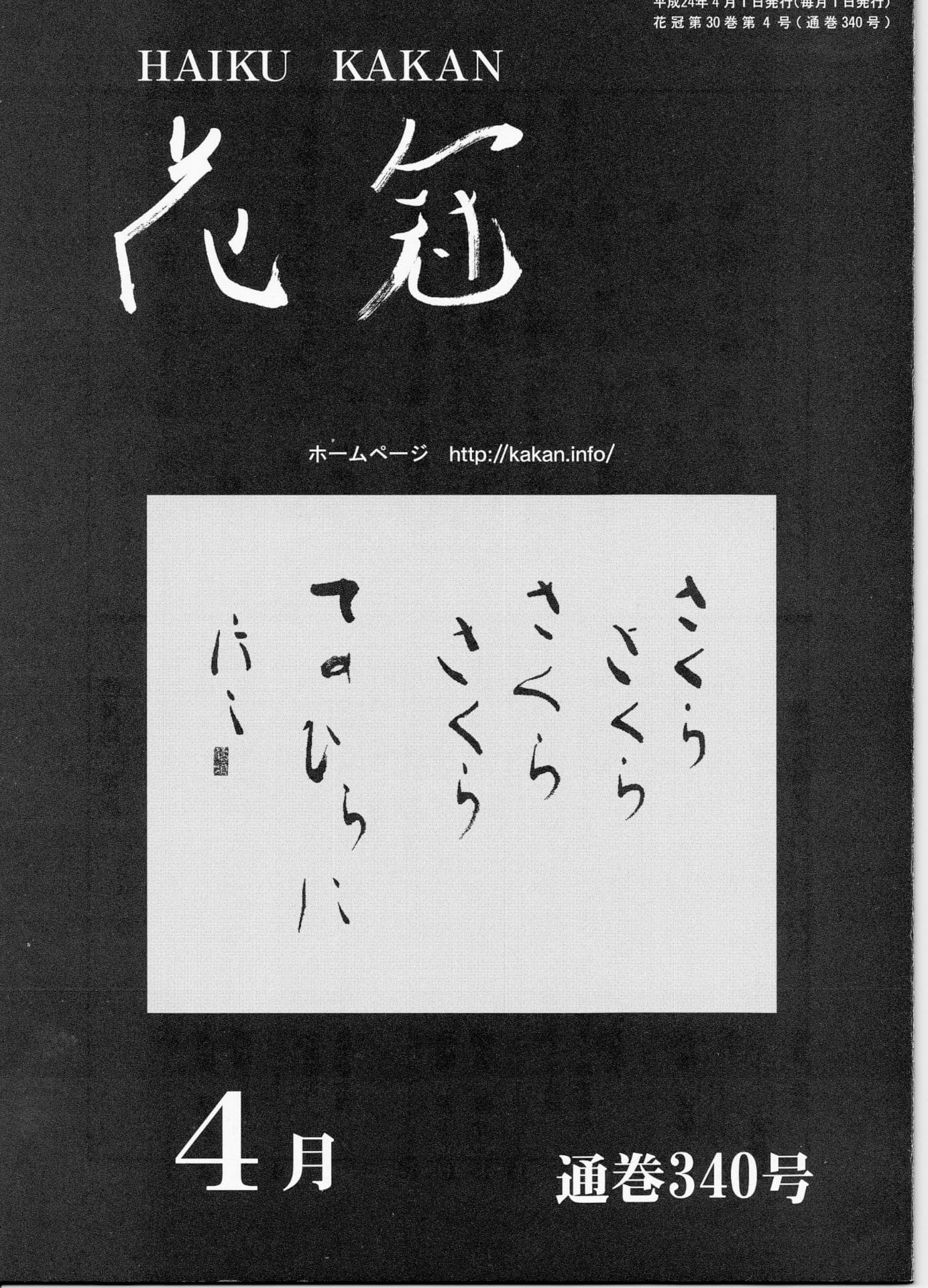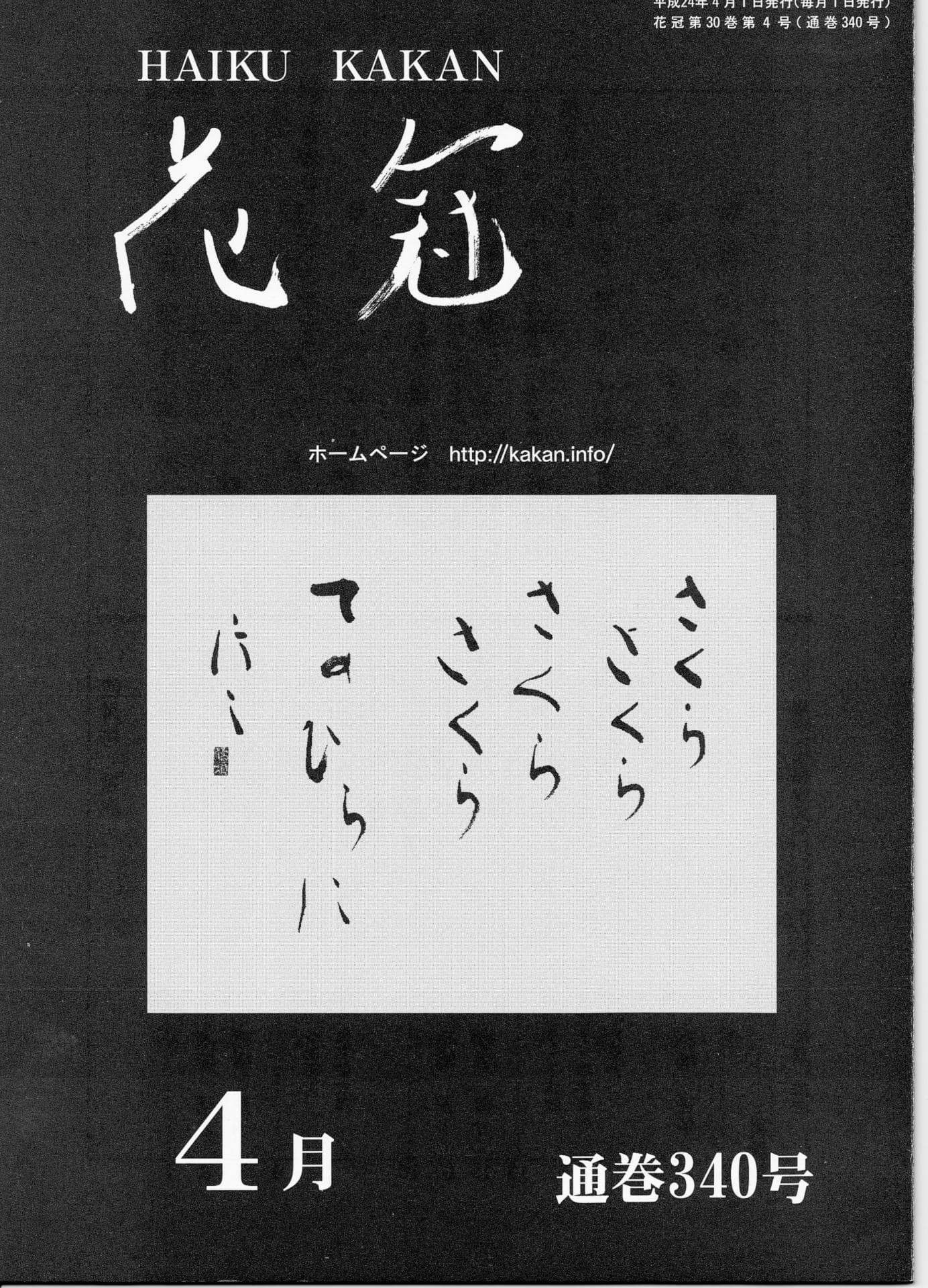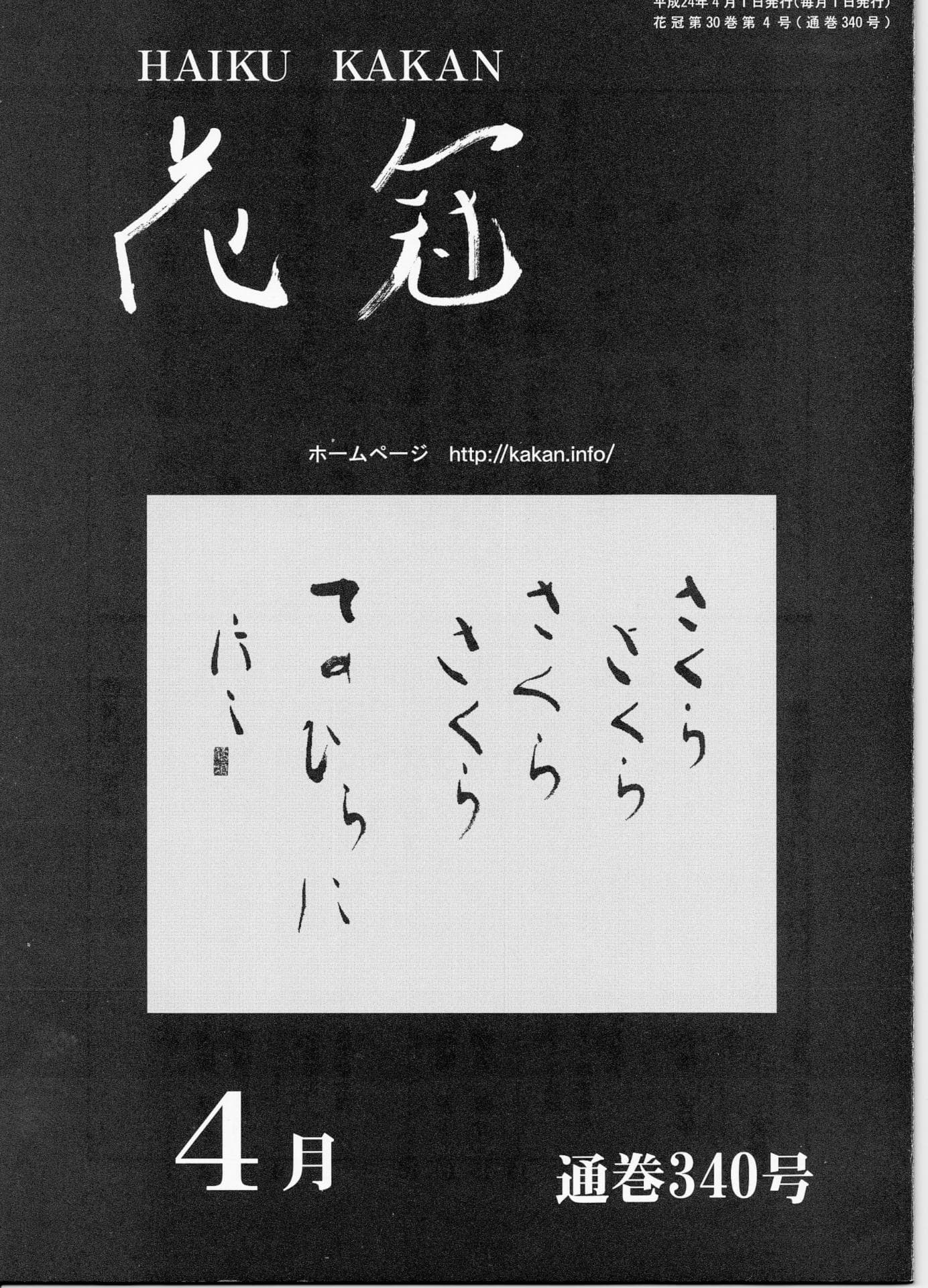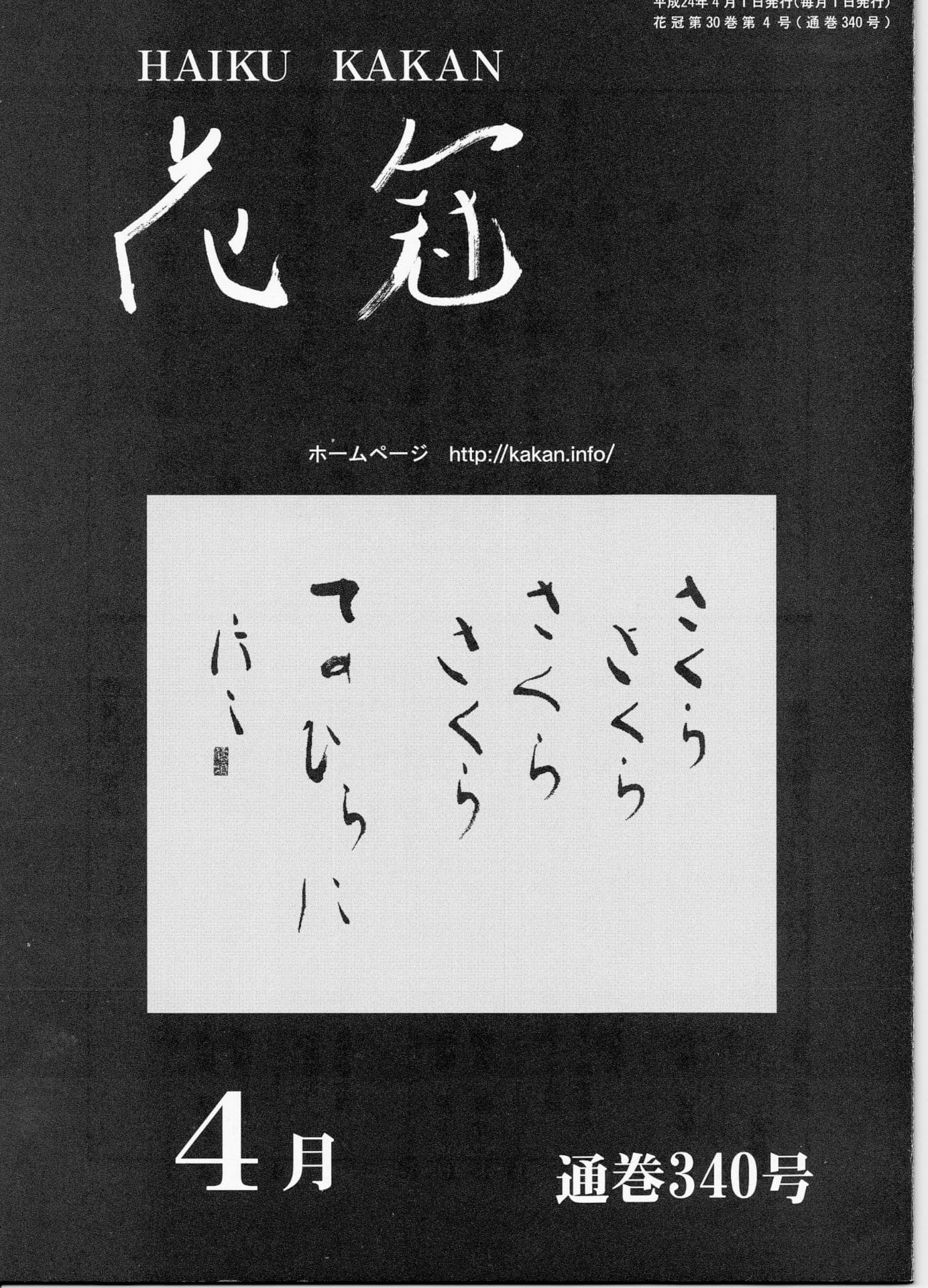
★聖書繰る野の青麦を思いつつ 正子
「一粒の麦もし死なずば」という聖書の言葉を思い出しました。青麦が揺れる季節、その心地よさの中で聖書の言葉を読んでおられます。(多田有花)
○今日の俳句
春の沖へ沖へとヨットのきらめく帆/多田有花
ヨットの観察をよくすべきなので、添削。春の沖へ出てゆくヨットの帆がきらめいて、沖にはもう夏が近づいている感じがする。(高橋正子)
○福山へ
昨日午前8時前の新幹線で娘の句美子と広島の福山へ。母の入院による見舞いのため。新横浜駅から福山駅までは、3時間22分の旅。二人の妹には鎌倉長島家の「切山椒」を土産に持参した。
○藤
★暮れ際に茜さしたり藤の花/橋本多佳子
★白藤や揺りやみしかばうすみどり/芝 不器男
★今日晴れて吾に空の青藤の白/高橋信之
藤は、つる性の落葉木本である。毎年4月から5月にかけて淡紫色または白色の花を房状に垂れ下げて咲かせる。園芸植物としては、日本では藤棚に仕立てられることが多い。白い品種もある。つる性であるため、樹木の上部を覆って光合成を妨げるほか、幹を変形させ木材の商品価値を損ねる。このため、植林地など手入れの行き届いた人工林では、フジのツルは刈り取られる。これは、逆にいえば、手入れのされていない山林で多く見られるということである。近年、日本の山林でフジの花が咲いている風景が増えてきた要因としては、木材の価格が下落したことによる管理放棄や、藤蔓を使った細工(籠など)を作れる人が減少したことが挙げられる。
◇生活する花たち「牡丹」(鎌倉・鶴岡八幡宮)



★スイートピー眠くなるほど束にする 正子
○今日の俳句
すかんぽの赤き穂が伸び揺れにけり/桑本栄太郎
すかんぽの穂は、伸びて来たばかりのころは、茶色がかった赤い色がやわらかで美しい。そよ風に揺れると、色に動きが出て楽しいものである。(高橋正子)
○鎌倉八幡宮の牡丹
★白牡丹といふといへども紅ほのか/高濱虚子
句集では、<はくぼたんというといえどもこうほのか>、と読ませている。その音が白牡丹の気品を表している。牡丹は四君子のひとつであるが、それを背景に「はく」「こう」と音読みにした意味もあろう。白い牡丹の花びらが重なり、重なると、ほのかに紅が差しているように見える。白牡丹のやわらかな花びらのかさなりと気品ある富貴の姿が美しく詠まれている。(高橋正子)
★牡丹のあとかたもなく花終へし/稲畑汀子
★林立の牡丹の裏側を歩く/岡本眸
★牡丹の香の流れ来るそこへと歩く/高橋信之
★牡丹の百花に寺の午(ひる)しじま/高橋正子
★ゆさゆさと百の牡丹も風のまま/黒谷光子
鎌倉の鶴岡八幡宮へ、昨日、信之先生は、一人吟行に出かけ、境内のぼたん園で牡丹の写真を撮って帰った。自宅から百メートル程西の日吉本町駅で横浜市営地下鉄グリーンラインに乗る。そこから四つ目の駅、センター北でブルーラインに乗り換え、新横浜駅、横浜駅等を過ぎ、戸塚駅で下車。戸塚駅からは、JR横須賀線で三つ目の駅、鎌倉駅まで。鎌倉駅から八幡宮までは徒歩、二の鳥居から三の鳥居へと、そこそこの道程があるが人波の絶えることがない。
鶴岡八幡宮(つるがおか はちまんぐう)は、神奈川県鎌倉市にある神社。武家源氏、鎌倉武士の守護神。鎌倉八幡宮とも呼ばれる。境内は国の史跡に指定されている。宇佐神宮、石清水八幡宮とともに日本三大八幡宮のひとつに数えられることもある。参道は若宮大路と呼ばれる。由比ヶ浜から八幡宮まで鎌倉の中心をほぼ南北に貫いており、京の朱雀大路を模して源頼朝が自らも加わり築いた。二の鳥居からは段葛(だんかずら)と呼ばれる車道より一段高い歩道がある。そこを抜けると三の鳥居があり、境内へと到る。境内へと入れば、すぐ右に、神苑ぼたん庭園の入口がある。源平池の池畔に造られた回遊式庭園の、ぼたん園である。源平池のほとりに内外の牡丹の名花、約1千株を集める。源平池の旗上弁天社では、藤の花が見頃を迎え、見事な白藤の盛りであった。
◇生活する花たち「牡丹・白藤①・白藤②」(鎌倉・鶴岡八幡宮)



★囀りに子の片言の鳥を呼び 正子
子供の幼児期を思い出します。一生懸命に鳥に呼び掛ける片言、かわいい時期でしたね。 (祝恵子)
○今日の俳句
花主と見上げふさふさ藤の房/祝恵子
「花主」は、風流。原句は、「見上げておりぬ」であったが、藤の房の観察をもう一歩進めて、「ふさふさ」と添削した。ふさふさとした藤房の豊かさが感じられる。(高橋正子)
○花水木
★松屋通りアメリカ花水木の盛り/宮津昭彦
★花水木われらはいつも下歩く/高橋正子
★花水木世の中いつか軽くなり/高橋正子
花水木(ハナミズキ、学名:Benthamidia florida)は、ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属の落葉小高木。北アメリカ原産。別名、アメリカヤマボウシ。ハナミズキの名はミズキの仲間で花が目立つことに由来する。また、アメリカヤマボウシの名はアメリカ原産で日本の近縁種のヤマボウシに似ていることから。樹皮は灰黒色で、葉は楕円形となっている。花期は4月下旬から5月上旬で白や薄いピンクの花をつける。秋につける果実は複合果で赤い。庭木のほか街路樹として利用される。日本における植栽は、1912年に当時の東京市長であった尾崎行雄が、アメリカワシントンD.C.へ桜(ソメイヨシノ)を贈った際、1915年にその返礼として贈られたのが始まり。なお、2012年に桜の寄贈100周年を記念して、再びハナミズキを日本に送る計画が持ち上がっている。
◇生活する花たち「梨の花・林檎の花・木蓮」(横浜市緑区北八朔)



★牡丹の百花に寺の午(ひる)しじま 正子
○今日の俳句
柿若葉吹き出す窓の明るさよ/安藤智久
桜が終ると、柿若葉が「吹き出す」ように燃え出てくる。柿若葉の明るい輝きに、窓は明るい季節へと変身する。(高橋正子)
○牡丹
★白牡丹といふといへども紅ほのか/高濱虚子(句集「五百句」大正時代)
句集では、<はくぼたんというといえどもこうほのか>、と読ませている。その音が白牡丹の気品を表している。牡丹は四君子のひとつであるが、それを背景に「はく」「こう」と音読みにした意味もあろう。白い牡丹の花びらが重なり、重なると、ほのかに紅が差しているように見える。白牡丹のやわらかな花びらのかさなりと気品ある富貴の姿が美しく詠まれている。(高橋正子)
原産地は中国西北部。元は薬用として利用されていたが、盛唐期以降、牡丹の花が「花の王」として他のどの花よりも愛好されるようになった。栽培は、春に花付の鉢植えが、秋に、苗木が売られるので、それで育てる。被子植物なので種からも育てられるが、開花まで時間がかかるので、一般的ではない。そのため、流通する苗のほとんどは、芍薬を台木に接ぎ木にしたものである。秋の苗木は根を切っているので、植えた翌春に咲いても、その後は株が弱り、次に咲くまで時間がかかる。あるいは枯れてしまう。そのため、花を惜しんで幹を切り二年後に期待するという方法がある。花付のものも花が終わると秋には鉢増しをする。土は腐葉土をたくさん含んだ肥沃なものを使用する。なお夏には休眠するので、葉は取る。
◇生活する花たち「藤・鈴蘭・牡丹」(横浜日吉本町)



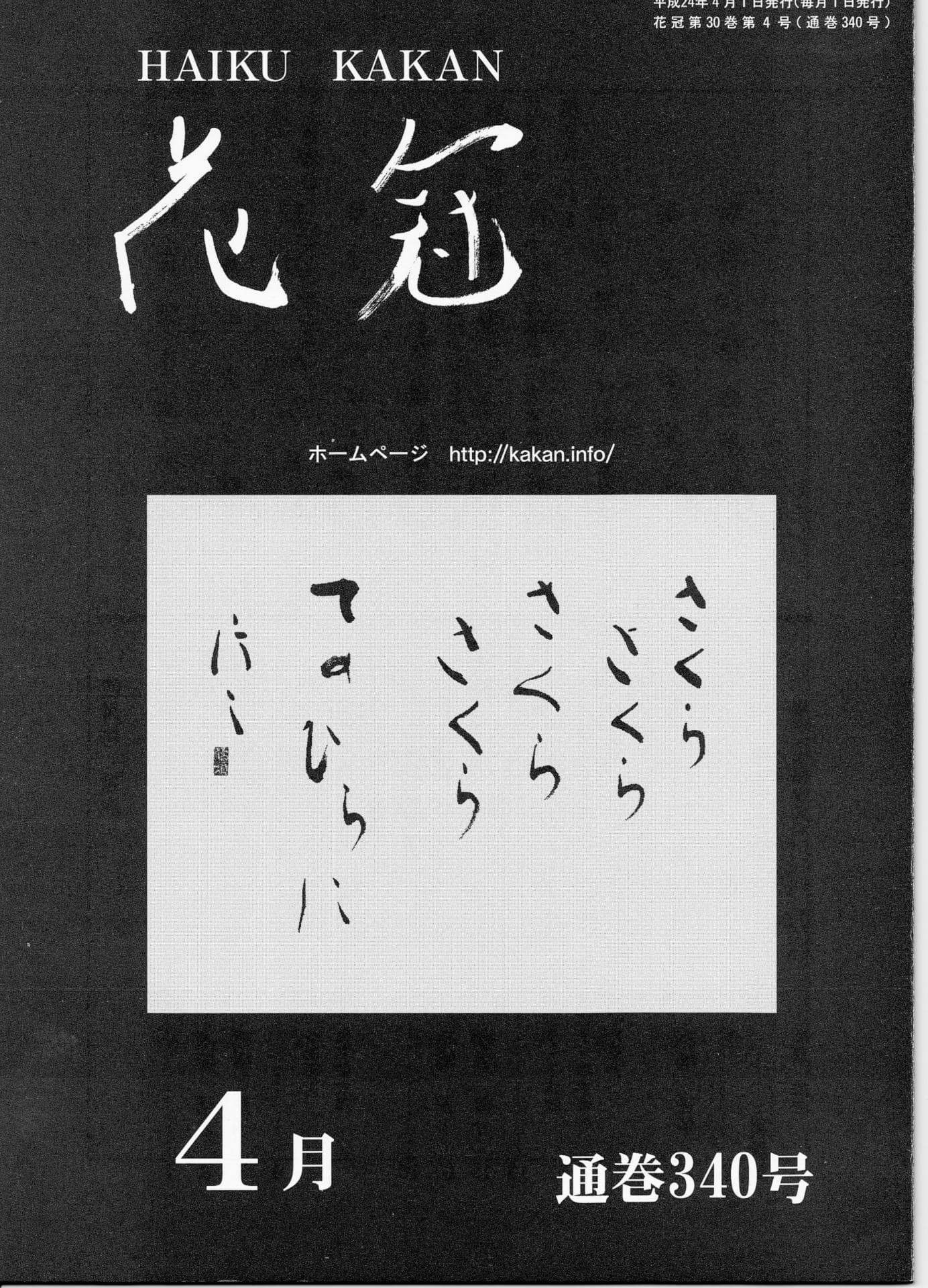
★明け初めし空の丸さよ柿若葉 正子
柿の若葉は小さく丸く萌え始め、だんだん茂と柔らかく萌黄色となって目を引き、明け初める空の初夏の景は素晴らしいですね。その対比が素敵な句だと思います。 (小口泰與)
○今日の俳句
さえずりや忽と眼間昼の火事/小口泰與
テーマは「さえずり」。気持ちよくさえずりを聞いていると、忽然と火事が見えた。現実であるが、さえずりの中にあってまぼろしのような火事である。(高橋正子)
○鈴蘭
★鈴蘭を掘りて鍬さげ汽車に乗る/高浜虚子
鈴蘭は、戦後の少女にとって、夢のような花であった。鈴蘭のように清らかに可憐な少女が実際に好もしいと思われた。しかし、私も友達も小学生のころは、鈴蘭の花を実際見たことはなかった。そして長じて実際に見たとき、花よりも葉の多さに驚いた。鈴蘭が咲くと、JAL便で日赤に鈴蘭が届いたということもニュースで報道された。この花を私の母親が好きで(好きであったことにも驚いたが)、わざわざ玉葱やじゃが芋を送ってくる荷物にドイツ鈴蘭を送ってきたことがあった。身近にあると、初夏のさわやかさがあって、和む花である。
★鈴蘭を束ねて翠の葉がきしむ/高橋正子
★鈴蘭の小さき花を振ってみむ/〃
◇生活する花たち「牡丹・さつき・藤」(横浜日吉本町)



小石川植物園
★たんぽぽの草の平らに散らばりぬ 正子
草萌えてまだ間のない原をあちこちに黄に染める、それがタンポポの力強さの一つだろうと思います。高く盛り上がるでもなく、ただ平らに草原を飾り、それも間をおいて散らばり咲いています。「草の平らに」の表現にタンポポの花の姿が生き生きと広がって見えます。(小西 宏)
○今日の俳句
蒲公英の花せめぎあい光りあい/小西 宏
蒲公英が明るい日差しの中に、びっしりの咲いている様子。一つ一つの花は可憐でありながら、せめぎあうほどの花の力。せめぐだけでなく、また、互いに光りあっている。確かな目である。(高橋正子)
○風船
★金の吹口虫の音籠り紙風船/中村草田男
★畳みぐせどほりに紙風船たたむ/加倉井秋を
★風船売り風船ふくらませば浮かぶ/高橋正子
広島の生家にて
★夏まつりの風船浮かせ子ら眠る/高橋正子
風船は、俳句の歳時記では春の季語で、ゴムなどの薄い膜でできた袋の中に気体を入れて膨らました後、その口を縛るなどして閉鎖し使用する玩具であるが、そのほか、販促(PR)、ギフトやイベントなどのバルーンデコレーション・風船飛ばし(バルーンリリース)、スポーツ応援、大道芸を含むバルーンアート、手品、科学実験イベント、風船バレー・風船割りなどのレクリエーションスポーツや遊戯施設、食品包装、医療分野などに使われている。もっとも用途が広いのはゴム製の風船。
◇生活する花たち「あけびの花・げんげ・白山吹」(横浜日吉本町)



小石川植物園
★やわらかに足裏に踏んで桜蘂 正子
桜が散ってしまったころからお天気は安定しはっきりと暖かい感覚になります。一年で最も過ごしやすい時期になり、そのころの伸びやかで心浮き立つような感覚が御句から伝わってきます。。(多田有花)
○今日の俳句
時はいまゆっくり流れ蝶の昼/多田有花
蝶の飛ぶ真昼。蝶の飛ぶ辺りは蝶の空間と時間となって、ゆっくりと時が過ぎている。春昼の気だるく長閑な時間が詠まれている。(高橋正子)
○虎杖(いたどり)
★紅斑ある虎杖思ふのみに酸し/山口誓子
★いたどりを折りとる時の音たしか/高橋正子
★いたどりの新芽の紅の尖りたる/ 〃
★川水を透かしいたどり群生す/ 〃
いたどりは、タデ科の多年生植物。別名は、スカンポ、イタンポ、ドングイ。ただし、茎を折るとポコッと音が鳴り、食べると酸味があることから、スイバをスカンポと呼ぶ地方もある。茎は中空で多数の節があり、その構造はやや竹に似ている。三角状の葉を交互につけ、特に若いうちは葉に赤い斑紋が出る。雌雄異株で、雄花はおしべが花弁の間から飛び出すように長く発達しており、雌花はめしべよりも花弁の方が大きい。夏には、白か赤みを帯びた小さな花を多数着けた花序を出す。
秋に熟す種子には3枚の翼があり、風によって散布される。そして春に芽吹いた種子は地下茎を伸ばし、群落を形成して一気に生長する。路傍や荒地までさまざまな場所に生育でき、肥沃な土地では高さ2メートルほどまでになる。やや湿ったところを好む。北海道西部以南の日本、台湾、朝鮮半島、中国に分布する東アジア原産種。昔の子供の遊びとして、イタドリ水車がある。切り取った茎の両端に切り込みを入れてしばらく水に晒しておくと外側に反る。中空の茎に木の枝や割り箸を入れて流水に置くと、水車のようにくるくる回る。
いたどりは、子どものころのおやつ代わりだったが、自分で採ったのを食べた記憶はない。田舎で育ったとはいえ、家の近くにいたどりが生えている場所はなく、山や沢などしかるべきところに行かなければない。あけび同様、いつも友達はどこで見つけるのだろうかと、半分、くやしい思いでいた。分けてもらったり、父親が山へいったときなど採って帰っていたのだろう、斑点のある茎をぽきっと折って、塩をつけて食べたが、酸っぱい。節を真ん中にして短く切って水に放しておくと、切り目を入れなくても、蛸の脚のように反るので、それを水車にして遊んだ。話は別だが、水車で遊んだのは、柿の花も水車にしてよく遊んだ。水車は小川の流れなどに持って行って遊ぶのだが、けっこうおもしろかった。
大人になっては、日本画に描かれたものをよくみた。新芽の紅や、斑点の面白さがよいのであろう。先日横浜市の鶴見川の土手に群生しているのを見た。2本折って持ち帰って、水に挿してある。「少し暑くなりかけた季節」が家内にある。
◇生活する花たち「豌豆の花・いたどり・梨の花」(横浜市緑区北八朔)



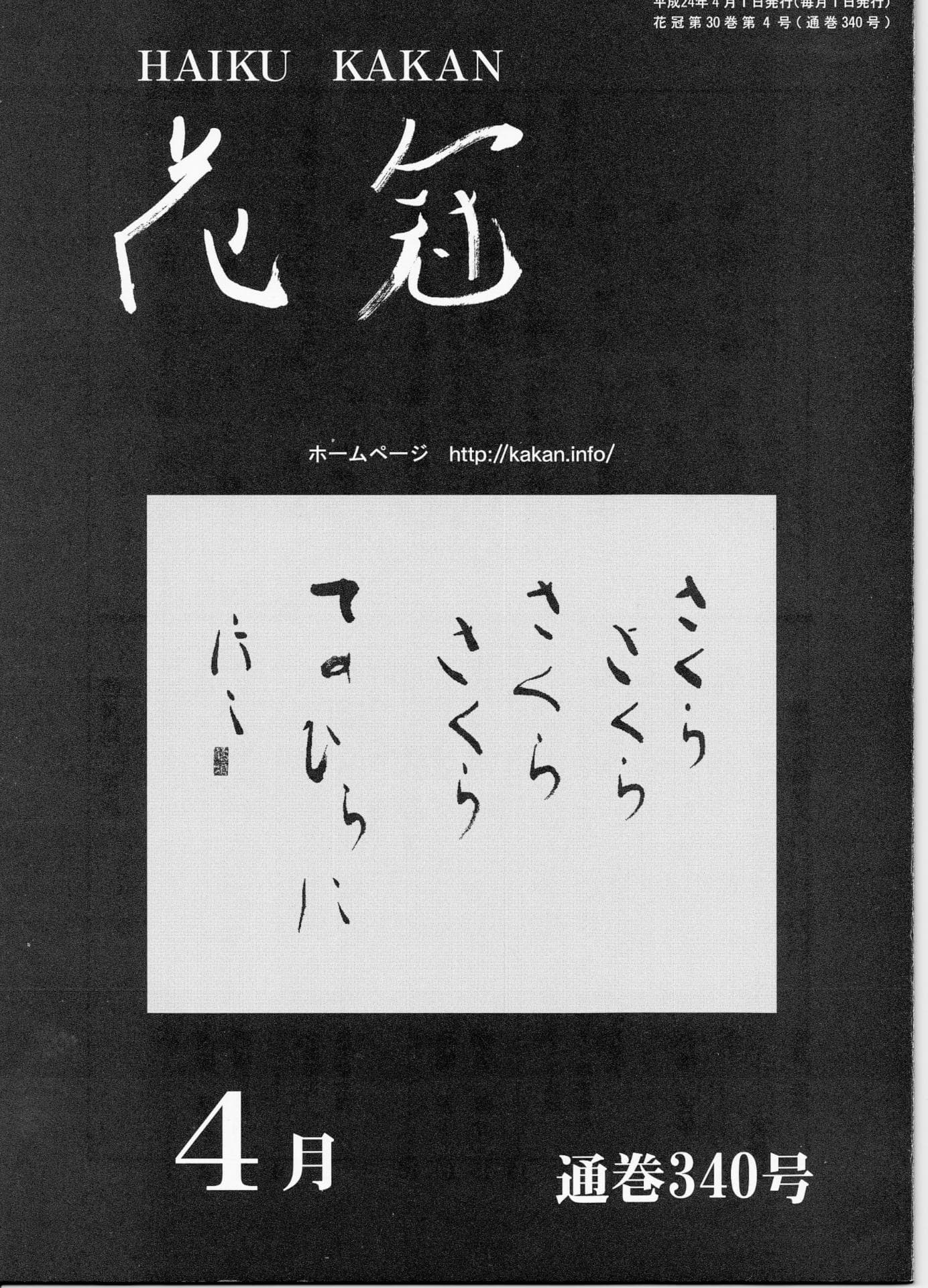
隅田川
★都鳥春の空より羽音させ 正子
都鳥が羽音をさせながら春の青空を飛んで行くのをご覧になったのでしょう。隅田川であること、都鳥であることで物語のように情景が広がります。(黒谷光子)
○今日の俳句
大寺の甍光りて緑立つ/黒谷光子
陽光が降り注ぐ大寺の甍を背景に、すくすくと伸びた松の緑の新芽。軸のようにすっくとぬきんでた姿に、旺盛な生命力を感じる。行く春の景色。(高橋正子)
○葱の花
★葱坊主子を憂ふればきりもなし/安住 敦
★葱の花ゆふべの鞄かかへ持ち/加畑吉男
★葱の花遠く並んでもその姿/高橋正子

葱の花はねぎぼうずと呼ばれ、形の面白さや、種となった野菜の終わりの情趣があって俳句にもよく詠まれている。子どもがいたずらにその頭を切り飛ばすこともある。種が充実するまで、豌豆や蚕豆、じゃが芋、玉ねぎが旺盛に育つ畑にあって、擬宝珠のような古い姿がじゃまくさい感じもした。熟れると切っての軒など風通しのよいところで乾燥させるが、その近くを通れば、種がぽろっとこぼれて、首すじに入ったりした。形は面白いが、ちょっと、すっきりしない気分の花である。(正子)
ネギ(葱、学名 Allium fistulosum’は、原産地を中国西部・中央アジアとする植物で日本では食用などに栽培される。クロンキスト体系ではユリ科、APG植物分類体系ではネギ科ネギ属に分類される。古名は「き」という。別名の「ひともじぐさ」は「き」の一文字で表されるからとも、枝分れした形が「人」の字に似ているからとも言う。ネギの花は坊主頭や擬宝珠を連想させるため「葱坊主」(ねぎぼうず)や「擬宝珠」(ぎぼし)と呼ばれる。「擬宝珠」は別科別属の植物「ギボウシ(ギボシ)」も表す。萌葱色は葱の若芽のような黄色を帯びた緑色のことである。日本では古くから味噌汁、冷奴、蕎麦、うどんなどの薬味として用いられる他、鍋料理に欠かせない食材のひとつ。硫化アリルを成分とする特有の辛味と匂いを持つ。料理の脇役として扱われる事が一般的だが、青ネギはねぎ焼きなど、白ネギはスープなどで主食材としても扱われる。ネギの茎は下にある根から上1cmまでで、そこから上全部は葉になる。よって食材に用いられる白い部分も青い部分も全て葉の部分である。西日本では陽に当てて作った若く細い青ネギ(葉葱)が好まれ、東日本では成長とともに土を盛上げ陽に当てないようにして作った、風味が強く太い白ネギ(長葱・根深葱)が好まれる。このため、単に「ネギ」と言う場合、西日本では青ネギを指し、白ネギは「白ネギ」「ネブカ」などと呼んで区別される。同様に東日本では「ネギ」=「白ネギ」であるため、青ネギについては「ワケギ」「アサツキ」「万能ネギ」「九条ネギ」などの固有名で呼ばれることが多いが、売り手も買い手も品種間の区別がほとんどついておらず、特に「ワケギ」「アサツキ」に関しては、その大半が誤用である。(ウィキペディアより)
◇生活する花たち「八重山吹・石楠花・梨の花」(横浜市緑区北八朔)



★春月の光りにも触る午前二時 正子
書きものをされたり、読書をされたり、あっという間に時間が過ぎていきました。窓から差し込む春月の光りが手許に届いていることに気が付きました。ふと時計に目をやると午前二時をさしていました。集中した時間を過ごされ、春月の光りにも触れることができ、幸せな喜びを感じられたように推察致しました。(藤田裕子)
○今日の俳句
日は昇り横たう春山まぶしかり/藤田裕子
「日は昇り」の「は」で、この句は詩となった。昇ったばかりの朝日を受け、まぶしく輝く春の山の、のびやかで堂々とした風景。(高橋正子)
○今日の秀句/フェイスブック句会
フェイスブック句会に毎日7・8名の投句があり、その中から<今日の秀句3句>を選ぶ。その中の1句にコメントを書く。発表は、投句の翌日になる。フェイスブックにシェアされると、ときには8名ほどの<友達>が、<いいね!>ボタンを押してくれる。読んでいただくことは、大変嬉しい反響である。
★桜蘂降り初む午後の風強し/多田有花
もう、桜蘂が降る季節になった。朝は静かだった風も午後には強く吹き、桜蘂を降らせた。「春が行く」感慨。(高橋正子)
★さくさくと土掘る音と囀りと/古田敬二
★春暑し六甲ライナー海の上/桑本栄太郎
○通草の花(あけびのはな)
★バスを待ちくたびれてをり花あけび/飴山 実
★藤村の地へ山一つ花あけび/稲垣陶石
通草(あけび)は、アケビ科の蔓性落葉低木の一種(学名 Akebia quinata)、あるいはアケビ属(Akebia)に属する植物の総称である。茎はつるになって他物に巻き付き、古くなると木質化する。葉は五つの楕円形の小葉が掌状につく複葉で、互生する。花は4~5月に咲き、木は雌雄同株であるが雌雄異花で淡紫色。花被は3枚で雄花の中央部には6本の雄しべがミカンの房状に、雌花の中央部にはバナナの果実のような6–9本の雌しべが放射状につく。雌花の柱頭(先端部)には、甘みを持った粘着性の液体が付いており、花粉がここに付着することで受粉が成立する。雌雄異花で蜜も出さないので受粉生態にはよくわかっていない点が多いが、雌花が雄花に擬態して雄花の花粉を目当てに飛来する小型のハナバチ類を騙して受粉を成功させているのではないか、とする仮説がある。ハエ類が甘みを持った粘着質を舐めに来る際に受粉していると考えられる。受粉に成功した個々の雌しべは成長して果実となり、10cm前後まで成長する。9~10月に熟して淡紫色に色づく。成熟した果実の果皮は心皮の合着線で裂開し、甘い胎座とそこに埋もれた多数の黒い種子を裸出する。この胎座の部分は様々な鳥類や哺乳類に食べられて種子散布に寄与する。
種子を包む胎座が甘みを持つので、昔から山遊びする子供の絶好のおやつとして親しまれてきた。果皮はほろ苦く、内部にひき肉を詰めて油で揚げたり刻んで味噌炒めにするなど、こちらは山菜料理として親しまれている。主に山形県では、農家で栽培されスーパーで購入することができる。また、東北地方などでは新芽(山形や新潟などでは「木の芽」と呼ぶ)をやはり山菜として利用している。その他、成熟した蔓はかごを編むなどして工芸品の素材として利用される。また、秋田県では種を油の原料としている。江戸時代から明治時代にかけては高級品として珍重され、明治以降生産が途絶えていたが近年復活した。
子どものころは、年上も年下も一緒に遊んだ。秋になるとあけびを採ってきたといって自慢げに見せてくれた。山のどのあたりにあるのだろうと、いつも不思議に思っていた。遠足などで山を越えるときに、あけびがある、などという声も聞いた。しかし、あけびの花は見たことがない。子どもだから、花があるなどと思ってもいなかった。さつま芋のような実が割れ、黒い種をミルクのような白いものが包んでいた。その姿だけ覚えていた。聞けば、受粉形態もおもしろい。
砥部焼の産地である砥部に住居を構えたおりに、家裏の川崖に木にあけびの花が咲き、実をつけた。山に入らねば見つからないのに、家の裏に出ればあけびが採れた。もちろん食べた。楕円状の葉もなかなかよいし、淡紫の花も、そして実も、果てはあけび籠となって、蔓まで身近になった。横浜では、近所の家に鑑賞用に植えられているので、見て楽しませてもらっている。蕾は、濃い紫の風船状で、それが割れて花が咲く。
★花あけば曇れる空のいや高く/高橋正子
★花あけび日差しそろそろ強くなり/高橋正子
◇生活する花たち「あけびの花・白山吹・をだまきの花蕾」(横浜日吉本町)



★独活放つガラスボールが水の玉 正子
○今日の俳句
楓の芽今開かんとして紅し/井上治代
楓の芽のかわいらしさと紅い色の美しさを端的に、みずみずしく詠んだ。「紅し」の言い切りが快い。(高橋正子)
○花冠6月号校了
午後、花冠6月号を校了とし、印刷にまわる。
花冠6月号の電子書籍を作成する。
http://kakan.info/km/k1206/
○俳誌花冠バックナンバー
http://kakan.info/km/
○電子書籍/e俳句ブック
http://kakan.info/01/
○蚕豆の花
★そら豆の花の黒き目数知れず/中村草田男
★蚕豆の花の吹降り母来て降り/石田波郷
★蚕豆の花に目を寄せ見ていたり/高橋正子
地中海、西南アジアが原産地と推測される。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土している。インゲンマメが普及する以前はソラマメは古代エジプトやギリシア、ローマにおいて主食とされていた。紀元前三千年以降中国に伝播、日本へは8世紀ごろ渡来したといわれている。古くから世界各地で栽培され、食用にされている。現在は南米、北米、ウガンダ、スーダンなどで栽培されている他、中華人民共和国河北省張家口で最高級品が栽培されている。高さ50cmほど。秋に播種する。花期は3−4月で直径3cmほどで薄い紫の花弁に黒色の斑紋のある白い花を咲かせる。収穫は5月頃から。長さ10−30cmほどのサヤには3−4個の種が含まれている。
蚕豆の花は、草田男の句にあるように、「黒き目」と見える斑がある。花は白というが、黒い斑のせいで薄紫に見える。蚕豆の花は、実を結ぶから取って遊ぶわけにはいかないが、葉で遊んだ。葉を折ると、半透明の薄い膜がはがれる。はがれるときれいな緑色が現れる。この緑色を出現させる遊び。遊びというほどのものではないが。
◇生活する花たち「げんげ・勿忘草・ミツバツツジ」(横浜日吉本町)