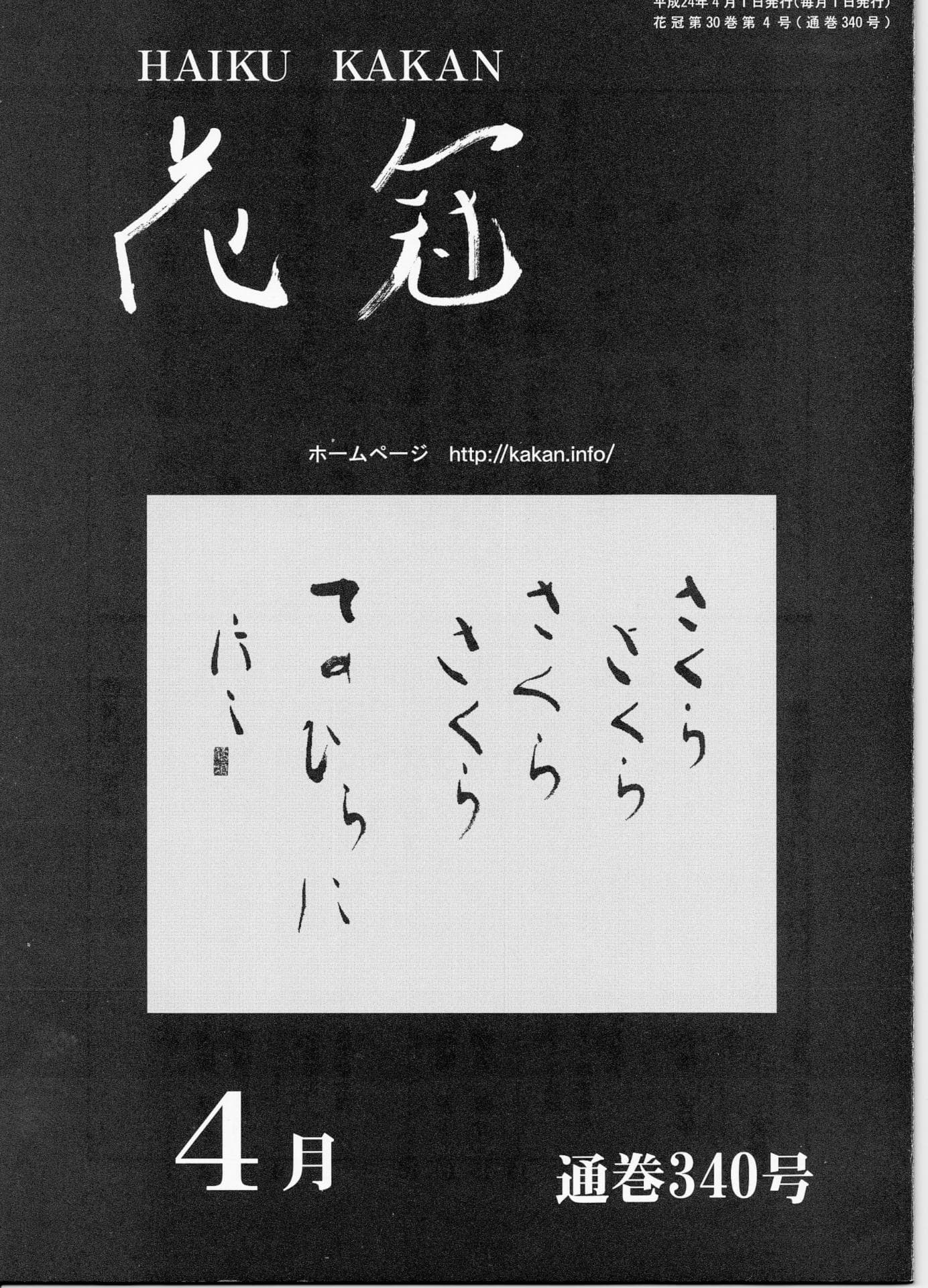
隅田川
★都鳥春の空より羽音させ 正子
都鳥が羽音をさせながら春の青空を飛んで行くのをご覧になったのでしょう。隅田川であること、都鳥であることで物語のように情景が広がります。(黒谷光子)
○今日の俳句
大寺の甍光りて緑立つ/黒谷光子
陽光が降り注ぐ大寺の甍を背景に、すくすくと伸びた松の緑の新芽。軸のようにすっくとぬきんでた姿に、旺盛な生命力を感じる。行く春の景色。(高橋正子)
○葱の花
★葱坊主子を憂ふればきりもなし/安住 敦
★葱の花ゆふべの鞄かかへ持ち/加畑吉男
★葱の花遠く並んでもその姿/高橋正子

葱の花はねぎぼうずと呼ばれ、形の面白さや、種となった野菜の終わりの情趣があって俳句にもよく詠まれている。子どもがいたずらにその頭を切り飛ばすこともある。種が充実するまで、豌豆や蚕豆、じゃが芋、玉ねぎが旺盛に育つ畑にあって、擬宝珠のような古い姿がじゃまくさい感じもした。熟れると切っての軒など風通しのよいところで乾燥させるが、その近くを通れば、種がぽろっとこぼれて、首すじに入ったりした。形は面白いが、ちょっと、すっきりしない気分の花である。(正子)
ネギ(葱、学名 Allium fistulosum’は、原産地を中国西部・中央アジアとする植物で日本では食用などに栽培される。クロンキスト体系ではユリ科、APG植物分類体系ではネギ科ネギ属に分類される。古名は「き」という。別名の「ひともじぐさ」は「き」の一文字で表されるからとも、枝分れした形が「人」の字に似ているからとも言う。ネギの花は坊主頭や擬宝珠を連想させるため「葱坊主」(ねぎぼうず)や「擬宝珠」(ぎぼし)と呼ばれる。「擬宝珠」は別科別属の植物「ギボウシ(ギボシ)」も表す。萌葱色は葱の若芽のような黄色を帯びた緑色のことである。日本では古くから味噌汁、冷奴、蕎麦、うどんなどの薬味として用いられる他、鍋料理に欠かせない食材のひとつ。硫化アリルを成分とする特有の辛味と匂いを持つ。料理の脇役として扱われる事が一般的だが、青ネギはねぎ焼きなど、白ネギはスープなどで主食材としても扱われる。ネギの茎は下にある根から上1cmまでで、そこから上全部は葉になる。よって食材に用いられる白い部分も青い部分も全て葉の部分である。西日本では陽に当てて作った若く細い青ネギ(葉葱)が好まれ、東日本では成長とともに土を盛上げ陽に当てないようにして作った、風味が強く太い白ネギ(長葱・根深葱)が好まれる。このため、単に「ネギ」と言う場合、西日本では青ネギを指し、白ネギは「白ネギ」「ネブカ」などと呼んで区別される。同様に東日本では「ネギ」=「白ネギ」であるため、青ネギについては「ワケギ」「アサツキ」「万能ネギ」「九条ネギ」などの固有名で呼ばれることが多いが、売り手も買い手も品種間の区別がほとんどついておらず、特に「ワケギ」「アサツキ」に関しては、その大半が誤用である。(ウィキペディアより)



コメント
お礼とコメント
お礼
正子先生「大寺の甍光りて緑立つ」の句を今日の俳句にお選びいただき、コメントも頂戴いたしありがとうございました。
コメント
隅田川
都鳥春の空より羽音させ
都鳥が羽音をさせながら春の青空を飛んで行くのをご覧になったのでしょう。隅田川であること、都鳥であることで物語のように情景が広がります。